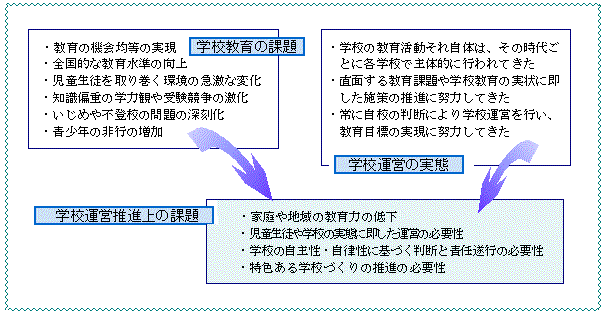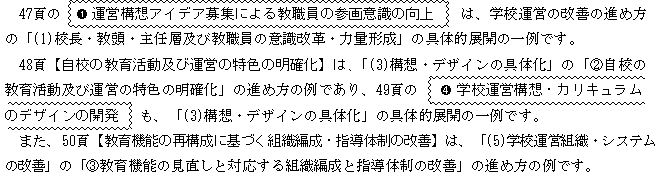岩手県立総合教育センター教育研究(1999)
主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善に関する研究
-先行研究や文献による資料の分析・考察をとおして-
目 次
1 はじめに
2 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の基本的な考え方
(1) 学校運営とは -定義、意義・機能、領域・内容-
(2) 主体的な教育活動の展開を目指す学校運営とは
3 主体的な教育活動の展開を目指す学校運営を進めるうえでの課題
(1) 日本の学校教育に関する歴史的変遷からみた学校運営推進上の課題
(2) 岩手県の教育活動に関する実態と課題
(3) 主体的な教育活動の展開を目指す学校運営を進めるうえでの課題
4 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の進め方の方向性
(1) 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の方向性
(2) 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の進め方
(3) 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営改善の進め方の具体的展開例
5 研究のまとめと今後の課題
6 おわりに
引用・参考文献
1 はじめに
21世紀を目前にし、学校は今それぞれに、新しい学校像を模索し学校改善に取り組んでいるところですが、学校週五日制や総合的な学習の時間の導入といった直面する課題、一人一人の教員や教員集団の意識改革、運営システムと方策の明確化等、課題が山積しており、学校運営の見直しなど具体的な対応策の検討が急がれているところであります。
こうした状況に際して、学校が、学校教育が新しい教育への抜本的な転換期にあることを自覚すること、さらに自校の学校運営について診断して課題を把握し、その課題に対応した自校の特色を生かした独自の改善の方向性を見いだし、運営構想を立てていくことが重要であると考えます。
この研究は、先行研究や文献から得た資料を分類・整理し、「主体的な教育活動」という視点からの分析・考察をとおして、今後の学校の在り方に見通しをもった学校運営についての「基本的な考え方」や「運営推進上の課題」を明らかにし、「学校運営の改善の進め方の方向性」を探るものです。
2 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の基本的な考え方
(1) 学校運営とは -定義、意義・機能、領域・内容-
この研究では、学校運営の定義、意義・機能、領域・内容について、次のように考えます。
<学校運営の定義>
| 各学校において、学校教育目標の効果的な達成をめざして教育活動を展開すべく、人的・物的諸 条件を整備し、その組織運営にかかる諸活動を管理・調整するとともに、教育活動の改善を求めて 営まれる機能である。 |
<学校運営の意義・機能>
学校運営の重要なポイントは、学校としての進むべき方向、ビジョンをつくることである。さら にその実現の方略を構想し、成員の協働関係と組織のダイナミズムをつくることも、運営が実現す べき機能である。
学校運営は、学校教育目標の達成に向けて行う営みである。どの領域・内容にしてもPDSのサ イクルに着目することが大切である。しかも組織的に行われるのが学校教育であるから、学校運営 計画(P)のいかんが重要である。学校運営計画には、(1)学校教育目標とその実現のための運営方 針、(2)運営の内容・方法・日程等、(3)子どもたちの特性・実態、(4)教育指導の方針、(5)運営評 価の観点の五つの条件を含むものでなければならない。 |
<学校運営の領域・内容>
学校運営が学校教育目標の効果的な達成のための諸条件の整備を内容とする関係上、その領域・ 内容は多岐にわたる。また、学校教育は個々の学校において編成した教育課程に従って実施される ものであるから教育指導のための組織と運営が最も重要な学校運営の仕事となるが、学校運営の領 域・内容は分類の仕方によってさまざまである。「運営」という側面からいえば、たとえば次のよ うになる。
(1)組織・運営 (2)教育課程 (3)生徒指導・教育相談 (4)学校保健・安全教育
(5)学年・学級経営 (6)庶務・経理
校種や学校規模等により学校運営の領域・内容が違うことはむしろ当然である。ただその原型としては、
(1) 教育指導 (2)研究・研修 (3)学校事務の三領域がある。 |
(2) 主体的な教育活動の展開を目指す学校運営とは
この研究では、「主体的な教育活動の展開」を「自主的・自律的に行う教育活動の展開」と同様に考え、「主体的な教育活動の展開をめざす学校運営」を「学校としての自主性・自律性を発揮して教育活動の展開を図ることをめざす学校運営」ととらえます。 「自主性・自律性」のとらえ方については、平成10年9月中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」の考え方を基盤としています。
「創意工夫」「地域に根ざした特色ある学校づくり」「自己判断と自己責任」「教職員一人一人の持てる能力・専門性の最大限の発揮」「教職員の意欲」「一致協力・積極的参加」「校長のリーダーシップの発揮」「個性の発揮」が、「主体的」のキーワードであり、具体的内容です。
3 主体的な教育活動の展開を目指す学校運営を進めるうえでの課題
(1) 日本の学校教育に関する歴史的変遷からみた学校運営推進上の課題
戦後の学校教育は、学力の向上を目指し、時代ごとにそれぞれの学校において問題解決学習や“学校づくり”論等、新しい教育運動の動きをとらえた様々な取り組みをとおして主体的に行われてきており、そのことは、教育の機会均等や教育水準の向上にも大きな効果をもたらしたと考えられます。
そうしたなかで、基礎学力の向上や児童生徒の個性に応じた指導の改善や教材の開発は、時代とともにますます重要となり、学校運営推進上の大きな課題となりました。また、その間、児童生徒を取り巻く環境の急激な変化等により、いじめや不登校の問題、青少年の非行の増加がみられるようになり、このことについての取り組みも急務となりました。
今後は、児童生徒の問題解決への意欲や能力を高めるために、総合的な学習の時間も導入されます。設定されたこの時間の内容をどうするかではなく、この時間が設定されたねらいに立ち戻り、この時間を活用して児童生徒をどういった手だてでどのように育てるかについて検討していきたいものです。
日本の学校教育に関する歴史的変遷から、次のように、今日に至るまでの学校教育の課題と学校運営の実態を踏まえ、今日の学校運営推進上の課題をとらえます。
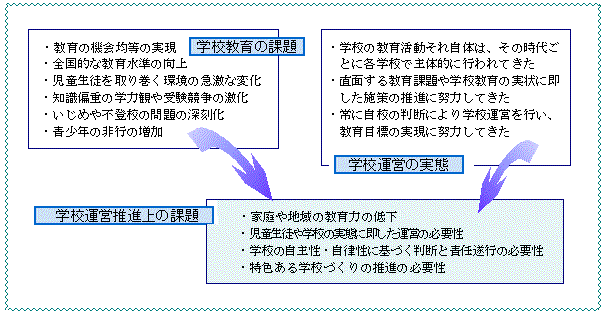
(2) 岩手県の教育活動に関する実態と課題
① 本県の小・中・高等学校における教育活動に関する実態
県小学校長会、県中学校長会及び県高等学校長協会より研究集録や記念誌等の資料を収集し、その研究テーマ・内容や教育活動についての報告の記録から、過去54年の本県の小・中学校及び高等 学校における教育活動の実態の推移について整理しまとめました。【表1】は、その結果です。
【表1】本県の小・中学校及び高等学校における教育活動に関する実態の推移
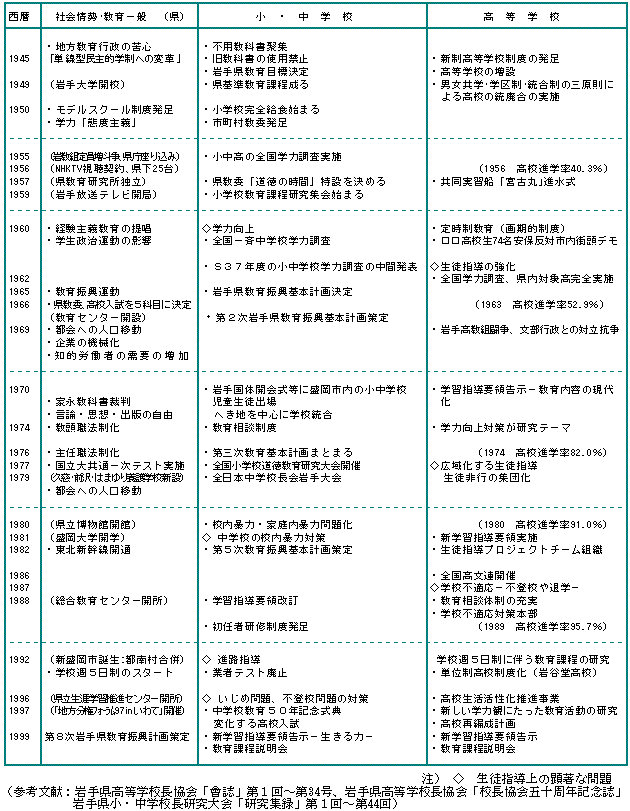
注) ◇ 生徒指導上の顕著な問題
本県では、戦後まもなく本県教育目標の設定や県規準教育課程の編成がなされ、市町村教育委員会が発足しました。小学校では、完全給食が開始となり、高等学校では新制高等学校制度が発足し高等学校の増設、男女共学・学区制・統合制が取り入れられてきました。その後も、小学校教育課程研究集会の開始、本県教育振興基本計画の策定と、教育振興が推進されてきています。また、高校進学率の推移をみると、1956年の40.3%から確実に上昇し続け、特に1963年から1974の約10年間の上昇率は52.9%から82.0%へと著しく、そして、1998年には97.7%と、ほとんどの生徒が高校へと進学するようになったわけです。これらのことから、教育の機会均等や教育水準の上昇の様子とそれを支えてきた本県の教育関係者の推進体制と努力の成果がうかがわれます。
学力に関しては、1960年代より現在に至るまで、学力向上のための様々な取り組みがなされてきているわけで、学力向上は本県の重要課題であるといえるでしょう。
また、児童生徒数の減少にともない、小・中学校では1970年代からへき地を中心に学校統合が行われるようになり、その後現在に至るまで年々少しずつ学校数は減少する傾向にあります。小規模校教育や複式学級における指導についても本県の重要な課題ととらえることができます。
生徒指導については、児童生徒を取り巻く環境の急激な変化にともない、1960年代の高校生の政治にかかわる活動や1980年代の中学生の校内暴力・家庭内暴力の問題、1990年代のいじめ・不登校問題というように、その状況が深刻化してきています。また、1980年代から高校に進学しても不登校や退学を起こすという傾向もではじめ、進路指導の必要性も増してきています。本県では1980年代には生徒指導プロジェクトチームが組織され、学校不適応対策本部の設置、教育相談体制の強化と、その対応に力を注いできています。
以上の本県の小・中学校と高等学校の教育活動に関する実態の推移についての分析・考察から、次の内容を問題点としてとらえることができます。(このうち①のみは、好ましい点です。)
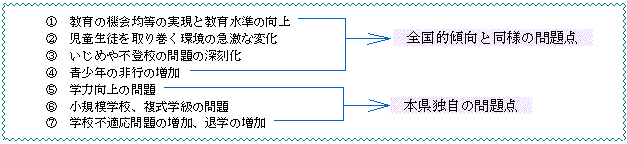
①~④については、全国的な教育問題と共通する部分もありますが、⑤⑥⑦は、本県がかかえる独自の問題点です。本県の教育活動に関する課題については、次のようにとらえます。
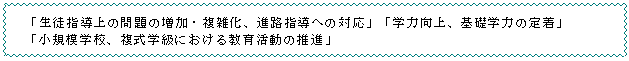
② 学校運営関係者がとらえている課題
当所は、平成10年7月、研究・研修推進上の必要から、県内から小・中学校及び県立学校の三分の一(小学校127校、中学校71校、県立学校28校)を抽出し、それらの学校とその小・中学校を管轄する57市町村教育委員会を対象に、「本県の学校教育推進上の課題」として最も重要と思われる内容2項目についてアンケート調査を行いました。その記述内容から、学校運営に関係すると思われる部分を抜粋し、その結果をまとめたものが【図1】です。
学校運営関係者の課題意識は、「新しい時代に対応した学校運営」に大きく傾いています。家庭・地域社会との連携の下に「地域を生かした特色ある学校運営を進めていくこと」「学校週5日制」「総合的な学習の時間の導入」「新教育課程編成」等の直面する課題への対応、これからの社会に向けての個々の「教員や教員集団の意識改革と資質・指導力の向上」を重要課題としてとらえています。
「小規模校の教育」や「学力向上」は、「本県としての独自の教育課題」です。あわせて、本県においても「児童生徒の実態」は年々変化してきており、「生徒指導上の問題の複雑化や進路指導への対応」「小・中・高の連携による指導」も重要課題です。
【図1】小・中学校、県立学校及び市町村教育委員会における学校運営関係者がとらえている課題
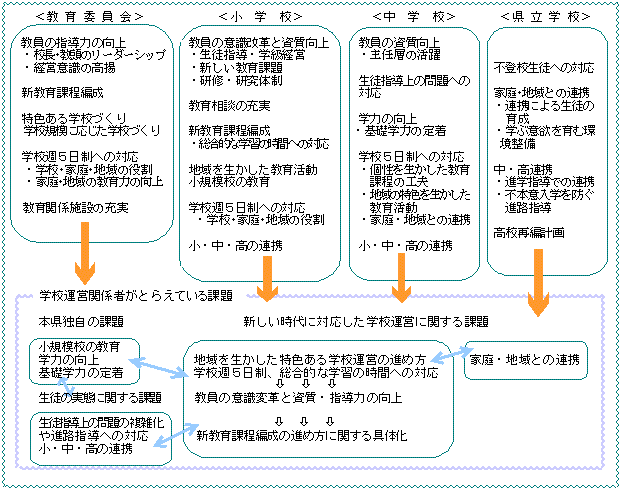
また、次頁【図2】は、平成11年7月27日~7月30日(前期)と11月8日~11月11日(後期)に実施された「平成11年度小・中学校教職経験者15年研修講座」の班別研究協議での研修者(小学校218名、中学校97名)の課題を集約し、学校運営推進の視点からまとめたものです。
教職経験15年の研修者は、小・中学校ともに、教務・研究・学年の主任や生徒指導主事の役につく者が多く、全体的に学校のなかで指導者的立場にあって学校運営に深く携わりその中核といえる存在です。研修者自身も運営という視点から学校教育をとらえようとする意識が高まってきています。したがって、学校運営推進上の課題をとらえるうえで、この315名の研修者の声は重要な部分を占めるものと考えられます。
研究協議のテーマは、「学校における組織的連携」(サブテーマ「保健室との連携」「豊かな心の育成」)と「総合的な学習の時間の導入」であり、学校運営の中核である「学校運営組織の連携」や「新教育課程編成」に関する課題を拾い出すことができると考えます。
「学校教育目標の具現化」における「目指す子どもの具体像、自校の特色づくりの方向性の明確化」、「教師の意識改革・資質向上」「組織的連携」「新教育課程編成」「指導内容・活動内容の関連性・系統性の明確化」、そして「学校が有する条件に応じた運営の具体化」「家庭・地域社会との共通理解と連携による指導」等が教職経験15年の研修者が課題としてとらえている内容です。
【図2】教職経験15年研修者の「学校運営組織の連携」と「新教育課程編成」に関する課題
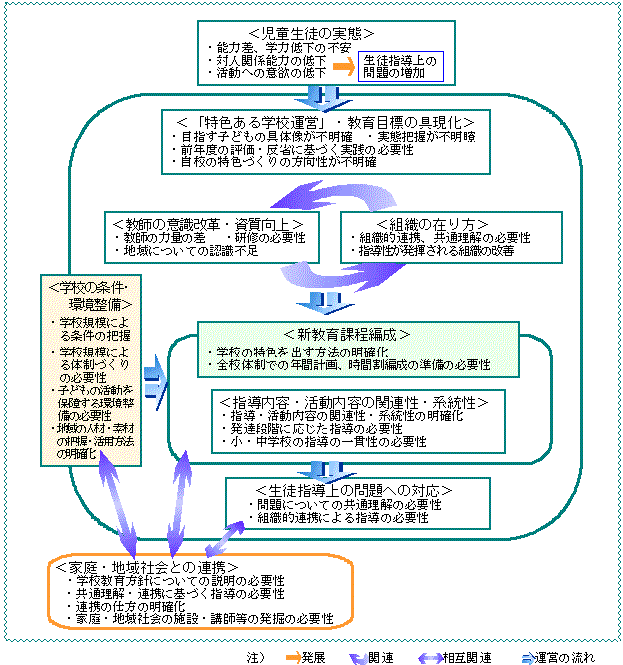
以上、小・中学校、県立学校及び市町村教育委員会における学校運営関係者がかかえる課題と、「平成11年度小・中学校教職経験者15年研修講座」における班別研究協議での研修者の課題を集約した結果から、本県の実態に基づく「学校運営推進上の課題」を、次のようにとらえます。
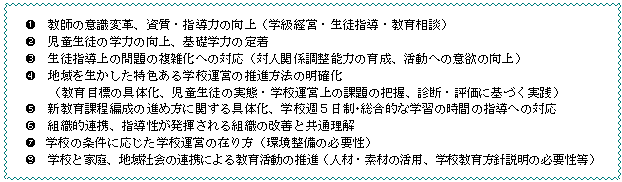
③ 本県教育課題に対する本県教育行政の対応
次の内容は、本県教育行政が打ち出した「第8次岩手県教育振興基本計画」における施策の、学校教育に関する内容の「
2 ゆとりの中で生きる力をはぐくむ学校教育の推進」についてまとめたものです。
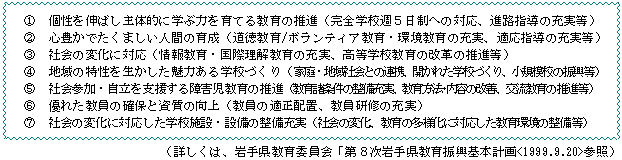
これらの内容は、今まで述べてきた本県としての課題に対応するとともに、教育を取り巻く社会の変化や今後の教育改革の動向の予想、そして将来の学校教育への展望に基づき設定された内容です。
(3) 主体的な教育活動の展開を目指す学校運営を進めるうえでの課題
前述の戦後の学校教育等の変遷、本県の過去の教育活動に関する実態と教育関係者のとらえている課題から全国と本県の実態に基づく「学校運営推進上の課題」をとらえ、あわせて中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」による「学校の在り方」に関する改善方策と本県の学校教育に関する施策の基本方向から、「主体的な教育活動の展開を目指す学校運営を進めるうえでの課題」について検討し、次頁【図3】にまとめました。
【図3】に示すように、「学校運営推進上の課題」について、全国と本県を比較した場合に、「生徒指導上の問題の複雑化」「児童生徒・学校の実態に即した運営の推進」「特色ある学校づくりの推進」等双方に共通の内容が多く、本県独自の推進上の課題を見出すことは難しいように思われます。 本県の特徴としてあげられるのは「学力向上」「生徒指導上の問題の複雑化、進路指導への対応」という児童生徒の実態に関する課題、「小規模校の振興」等の学校の有する条件に関する課題です。
したがって、本県における各学校が主体的な教育活動の展開を目指す学校運営を推進していくうえで、「本県としては、どういった内容を課題としておさえていくべきか」と考えるてみると、児童生徒数が減少し学校規模が小規模化する現状のなかで、中央の都市部と比較して、豊かな自然環境と地域社会に密接な人間関係がまだ多く残されているという条件を生かし、家庭や地域社会との共通理解と連携によって、一人一人の児童生徒に豊かでたくましい心を育成し学力を向上させるためのきめ細かな教育活動を展開していくことであろうかと考えます。
【図3】主体的な教育活動の展開を目指す学校運営を進めるうえでの課題
4 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の進め方の方向性
(1) 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の方向性
次頁【図4】は、前述の学校運営推進上の課題と先行研究における学校運営の方策についての分析と考察をもとに、主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の方向性について、必要と思われる内容とその内容のかかわりをまとめたものです。なお、

の内容は改善の具体的な展開例を示します。
これらの内容のうち、(2)から(4)は、「計画的推進」の内容であり、「
(2) 学校としての課題と改善の方向の明確化
⇒ (3) 構想・デザインの具体化 ⇒ (4) 教育課程の編成・運用の弾力化」と、「診断(S)
⇒ 改善(I)のための計画(P)」の部分を示し、「
計画(P)- 実践(D)-評価(S)- 改善(I)」という一連のサイクルの中核に位置づけられます。
「 (5) 学校運営組織・システムの改善」「
(8) 地域住民の学校運営への参画」は、学校運営の「計画的推進」を、組織的にどのようにサポートしていくかという「組織的推進」の内容であり、「(6)学校の事務・業務の効率化」「(7)学校施設・設備の整備・充実」は、計画的推進が、「条件整備」の方向に具体化した内容です。
そして、「 (1) 校長・教頭・主任層及び教職員の意識改革と力量形成」は、これら全ての推進内容を根底から支える学校運営推進の基盤といえる内容です。
(2) 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の進め方
「計画的推進」「組織的推進」「意識改革」の内容は、学校運営の基本であり普遍的な内容です。また、その進め方も極めて自然で当たり前といえます。学校運営推進は、これら基本の内容を、当たり前に確実に実行していくことであり、本県の学校運営改善の方向についても同様であると考えます。
本県の児童生徒の実態や学校を取り巻く自然環境や地域社会等の条件に即して、学校運営推進の基本的な内容と進め方に基づき、「心の育成」「学力向上」のためのきめ細かな教育活動を展開していくことを、本県の改善の方向としてとらえて進めていきたいと考えます。
(3) 主体的な教育活動の展開を目指した学校運営改善の進め方の具体的展開例
主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の方向性について検討するために収集した、関係する先行研究や文献からの資料をもとに、現時点での改善の進め方の具体的展開例を別冊【主体的な教育活動の展開を目指した学校運営改善の進め方の具体的展開例集】にまとめました。そのなかから、四つの例を紹介します。
【図4】主体的な教育活動の展開を目指した学校運営の改善の方向性
この研究について、成果として得られたのは次のことです。
① 全国の先行研究や文献から得た「学校運営の定義、機能・意義、領域・内容」「学校運営の在るべき姿」等に関する資料を整理し、主体的な教育活動の展開を目指す学校運営にかかわる基本的な考え方について明らかにすることができたこと
② 本県の小・中学校長会及び高等学校長協会から得た資料による戦後から今日に至るまでの本県の「教育事情の概要」「児童生徒の実態」「対応する学校における具体的教育活動」の推移とそれらのかかわりについての分析・考察や当所が実施した「本県の学校教育推進上の課題に関する調査」「教職経験者15年研修講座での班別研究協議」の結果の分析・考察等から、本県の学校運営を進めるうえでの課題を把握することができたこと
③ 全国的な視野からとらえた学校運営を進めるうえでの課題と本県としての学校教育推進上の課題の分析・考察をもとに、主体的な教育活動が展開できるような、「学校運営構想の具体化」「学校運営組織の改善」等の学校運営の改善の進め方についての方向性を探ることができたこと
また、方向性の検討のために収集した関係する先行研究や文献からの資料をもとに、現時点での改善の進め方の具体的展開例をまとめて提示することができたこと
今後の課題に関しては、研究を進めるなかで、学校としての教育課題や運営推進上の課題の把握なしには運営改善の方向性が定まらず、主体的な教育活動の展開が望めないことから、学校運営についての診断を行うことの重要性を確認しました。「診断(S)-改善(I)=『ビジョン・計画(P)-方略(D)』-診断(S)-改善(I)」という流れにそって、「主体的な教育活動の展開が可能であるか」という視点で、自校独自の課題と条件に即した診断を行っていくことが重要であると考えます。
したがって、自校の特色を生かした独自の運営改善につながる具体的な方策について再検討・吟味していくことを課題としたいと思います。
6 おわりに
この研究は、今日の学校運営状況に問題状況を見出し改善の手だてを組むというものではなく、学校が新しい学校像を模索し学校改善に取り組んでいる状況に際し、これからの学校運営の方向性について一緒に考え、少しでも学校の役に立つことを、という発想で始めたものでした。
現実の教育情勢や学校の教育活動の状況や児童生徒の様子は変化がはやく、県内の学校のニーズに対応する研究結果を出せるかという不安は大きく、難しい研究に感じられました。やはり、学校の先生方の生きた言葉や実践をもっと取り入れたいと感じました。
これからの研究の方向性としては、作成した運営診断表を実際に学校で活用してもらい、今年度研究をとおして明らかにした「学校運営の改善の方向性」の内容に、診断結果からとらえた学校の課題をインプットし、学校の要望に応じた改善のプログラムを組んで提示する、その後の経過にそって学校と一緒になって方法を工夫していく等、学校独自の課題と学校が有する条件に応じた運営改善の方略について検討していきたいと考えます。
「学校に、検証のための実践をお願いする」という考え方ではなく、研究に携わり一緒に実践していただくことで、確実に学校も良い方向に変化していくような研究でありたいと思います。
引用・参考文献
<引用文献>
岩手県教育委員会 「第8次岩手県教育振興基本計画 <1999.9.20> 」
日本特別活動学会紀要第6号 P.76「これからの学校教育と特別活動の役割」 1997
<参考文献>
平成10年10月中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」
平成11年度小・中学校教職経験者15年研修講座資料「班別研究協議まとめ」
岩手県小・中学校長研究大会「研究集録」(第1回~第44回)
岩手県中学校長会「岩手県中学校教育50年記念史」 1998
岩手県高等学校長協会「會誌」第1号~第34号
岩手県高等学校長協会「校長協会五十周年記念誌」 1998
平成11年度岩手県高等学校教頭協議会研究年報「校長を補佐し管理運営にかかわる教頭の役割について」 1999
第28回教育展望セミナー研究討議資料「魅力あふれる学校の創出Ⅱ・創る喜びの共有」 教育調査研究所 1999
教育展望12月号 特集「特色ある教育活動の創造」 教育調査研究所 1999
教職研修12月号 特集「2000年の学校経営戦略(1)」 教育開発研究所 1999
教職研修1月号 特集「2000年の学校経営戦略(2)」 教育開発研究所 2000
高倉 翔 監修 教職研修「自主・自律の時代の学校」 教育開発研究所 1999
菱村幸彦 監修 教職研修「戦後の教育の論争点」 教育開発研究所 1994
中野重人 編集 教職研修「特色ある教育課程を工夫する」 教育開発研究所 1998
高倉 翔 監修 教職研修「創意を生かす新教育課程の編成・実施・評価」 教育開発研究所 1999
中留武昭 著 「戦後学校経営の軌跡と課題」 教育開発研究所 1984
中留武昭 著 「変化の時代の学校経営」 教育開発研究所 1995
牧 昌見 編 「新学校用語辞典」 ぎょうせい 1995
児島邦宏 著 「学校経営の創意と改善」 ぎょうせい 1996
尾木和英 著 「校内研究事典」 ぎょうせい 1999
全国教育研究所連盟編 「新しい学校を創る」 ぎょうせい 1998
福岡県教育研究所連盟編 「学校を活性化する経営診断と経営改善」 第一法規 1998
中留武昭 著「学校改善を促す校内研修」 東洋館出版社 1994
牧 昌見・高橋静男・田島惟克 編 「学校改善を深める経営診断」 東洋館出版社 1994
高階玲治 編 「学校改善をめざす組織づくり」 東洋館出版社 1994
杉山正一 編著 「小学校実務と事例シリーズ:研究主任の実務と事例」 東洋館出版社 1980
日本特別活動学会紀要第6号 P.76~78「これからの学校教育と特別活動の役割」 1997
八尾坂修・高田和裕 「学校経営改善を進める学校評価票の活用」 奈良教育大学教育実践研究指導センター研究紀要 No.7抜粋 1998
はじめに戻る
岩手県立総合教育センター
〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1
TEL:0198-27-2711(代)
FAX:0198-27-3562(代)
Copyright(C) The Comprehensive Educational Center of Iwate