−各教科の指導内容に即した教材の開発とカリキュラムへの位置付けをとおして− |
||||||||||
| 情報教育室 工藤恭介 |
||||||||||
|
||||||||||
| 情報教育室 > 研究の推進 > 小学校におけるコンテンツ活用 > アンケート集計結果 |
|
|
−各教科の指導内容に即した教材の開発とカリキュラムへの位置付けをとおして− |
||||||||||
| 情報教育室 工藤恭介 |
||||||||||
|
||||||||||
|
|
| 調査項目(アンケート形式) |
| ▲このページの先頭へ |
|
|
|
| ▲このページの先頭へ |
| 【1】授業における教育用コンテンツの活用について | |
| 1-1 貴校では、授業で教育用コンテンツを活用していますか。 | |
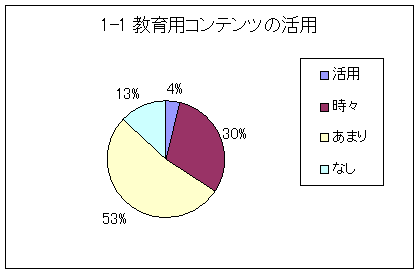 |
☆「活用している」と「時々活用している」を合わせると34%であり、「あまり活用していない」と「活用していない」を合わせると66%であった。 |
| 1-2 画像を中心とした教育用コンテンツの活用は、学習指導に役立つと思いますか。 | |
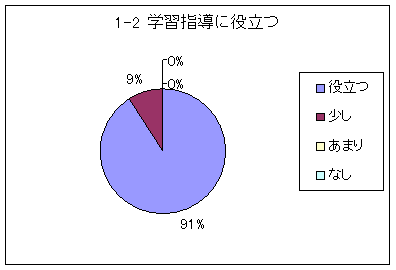 |
☆「役立つと思う」と「少し役立つと思う」を合わせると100%であり、「あまり役立たないと思う」と「役立たないと思う」を合わせると0%であった。 |
| 【2】教育用コンテンツの年間指導計画への位置付けについて | |
| 2-1 貴校では、活用場面を年間指導計画へ位置付けていますか。 | |
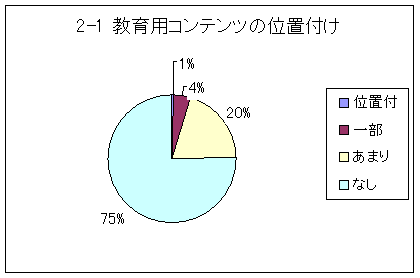 |
☆「位置付けている」と「一部位置付けている」を合わせると5%であり、「あまり位置付けていない」と「位置付けていない」を合わせると95%であった。 |
| 2-2 教育用コンテンツの年間指導計画への位置付けは、学習指導に役立つと思いますか | |
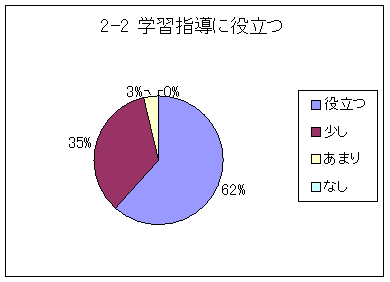 |
☆「役立つと思う」と「少し役立つと思う」を合わせると97%であり、「あまり役立たないと思う」と「役立たないと思う」を合わせると3%であった。 |
|
|
| 調査結果 II (教育用コンテンツの主な活用実践) |
| ※教育用コンテンツを活用した授業実践例を、先生方から紹介していただきました。 |
| ▲このページの先頭へ |
| 教科等 | 学年 | 活用実践 |
| 国語 | 共通 | ○タイピング(ローマ字)など ○「聞く・話す」の工夫したスピーチを録画 ○招待状作り ○学校ニュース ○ことばあつめ(同音異義語、ことわざ、四字熟語など) ○レポート作成に活用 |
| 算数 | 共通 | ○計算の仕方、タイル操作の仕方等のプレゼンテーション習熟練習 ○授業の例題を解く場面で、プロジェクタでわかりやすく見せる ○立体や面積のシュミレーション ○平行、垂直の書き方(動画) ○図形の面積の求積 |
| 生活科 | 共通 | ○お絵かきソフトの使い方 |
| 理科 | 共通 | ○植物の成長(発芽、根の様子)の画像 ○種子の発芽の様子を動画により提示し、種子のどの部分がどのように変化するのか確かめさせる ○植物や生き物(メダカ)の動画コンテンツを入手して、プロジェクタで提示 ○子どもたちが採取した草花をデジカメにとり、それを静止画で見せ、植物の観察に活用している ○植物や昆虫の成長の画像(静止画、動画)を見せている ○動植物の成長の学習のまとめで、動画を見せ学習内容を整理 ○発芽の様子(動画)、細胞分裂の様子(動画など)実際に観察することが困難なものを見せるようにしている ○植物の成長や太陽の動きなど、時間の経過と変化、動きを示す方法の一つとしての画像の活用 ○静止画や動画を提示して、植物の成長や地球の自転等について理解させる ○モンシロチョウの羽化の画像 ○こん虫の成長を画像で見せる ○昆虫のからだのつくりの学習(パズルのように昆虫のからだを組み立てることでからだのつくりを学ぶ) ○デジタルカメラとテレビを活用して、教科書や資料集の画像等を提示している ○太陽の動きの画像 ○天体の動き(変化)をシミュレーションで見せる ○気象衛星の画像の活用 ○実験器具のあつかい方(安全な使い方と危険な使い方の例)の画像 ○実験観察の再現としての使い方 ○理科ネットワークのコンテンツを活用して、各単元で必要に応じて利用している ○星や月の動き、昆虫の羽化等、観察が難しいものについての画像の提示 |
| 3年 | ○NHK学校放送、「モンシロチョウの育ち方」について、パソコンにインターネットで取り入れて、学級ごとに視聴した視聴は、プロジェクタで映し出し、一斉に行った。当初、児童用それぞれのパソコンにより視聴することも考えたが、個々のパソコンでは、となりのパソコンとの音声のずれが生じて聴きにくくなるので、プロジェクタを使用した | |
| 4年 | ○「空気と水」ねらい:(1)注射器に閉じこめられた空気を上から手(指)で押し縮め、もどる様子をつかませる。前時の振り返りとして動画録画した教材をプロジェクタで投影し、前時の実験を想起させるために活用した。(2)水そうに向けた空気でっぽうの玉が飛び出す瞬間をつかませる ○「星座」についての画像 ○ヘチマの育ち方の画像 ○熱の伝わり方の実験を撮影し再現しながら検討する(銅板や水中でのおがくずの動き) |
|
| 5年 | ○「天気の変化」インターネットの動画利用 ○インターネットで取り込んだ天気図をもとに気象についての学習をする ○台風の進路の画像 ○天気の様子(ソフト、www上のコンテンツ) ○天気の移り変わりを動画で見る ○気象衛星の雲写真や天気予報、アメダスの雨量情報などをインターネットから出して見せた ○天気図(雲の動き)をダウンロードして活用、毎日の気温をグラフに表す ○雲や台風の動きを動画によって見せ、天候の変わり方や台風への理解を深めさせる ○天気と気温の変化…雲の写真から天気の変わり方を考える ○天気(雲の動きと天気の変化)の画像 ○メダカの卵の観察の中での「メダカの交尾」。そのシーンを実際に子どもに見せるのは不可能。教育用コンテンツを見せて、メダカの卵は受精したものが発生を進めることを説明 ○メダカの卵の成長…デジカメでとった画像をパソコンに取り込み、成長の過程を学習した ○魚や人のたんじょう…メダカの卵からかえるまでの動画を提示し、卵の中の変化を見る ○「魚や人のたんじょう」…静止画を使いFDに入れている ○人のたんじょう(発生のプロセス、他の動物との比較)の画像 ○雲の動きをHPより収集してサーバに保存。子どもたちが適時、それを確認のために使用する |
|
| 6年 | ○「動物のからだのはたらき」呼吸、血液、消化(VTR)の画像 ○からだのはたらきで、実験等で扱えない実際の体内での様子を呼吸、消化、血液のはたらきの仕組みを動画で観察することで理解を深めた ○「動物のからだの働き」…静止画を使いFDに入れている ○動物の体のはたらき(消化のしくみ、呼吸と血液の流れ、心臓のはたらき)の画像 ○植物の役割を映像を参考に学習した |
|
| 社会 | 共通 | ○静止画や動画を導入段階での関心を持たせることに活用したり、課題解決のための資料として活用したりした ○校外学習の調べ学習(インターネット) ○人物辞典の画像 ○導入での興味意欲の高揚としての画像の活用 ○まちの様子等をビデオ、デジカメで撮影し、導入で利用 ○資料提示として…導入場面等、PCとプロジェクタで ○実際に見ることができないもの(自動車工場の仕組み)などのことについて、インターネットやソフトを使って活用している |
| 3年 | ○学区探検や校外学習の様子を撮影し、その後の授業に生かす(学校のまわりの様子) | |
| 4年 | ○「わたしたちのくらしとごみ」…ごみ処理場のしくみとはたらきをインターネットから出して見せた ○暖かい地方と寒い地方のくらしを調べる学習において、沖縄県や北海道のホームページや産業の様子などを見られるホームページにリンクし、違いやそれぞれの特徴を理解する手助けとした ○学区探検や校外学習の様子を撮影し、その後の授業に生かす(工場見学、消防署、ごみ処理施設見学) ○下水道、交通安全、消防等の施設見学の際の画像をまとめでの活用 |
|
| 5年 | ○「米づくりが盛んな庄内平野」インターネットの画像活用 ○「米づくり」稲の育て方(成長でも扱う予定)…稲の開花、受粉の様子もあれば利用したいと考えている ○「食料生産を支える人々」…米の生産地を調べたり、漁獲高について活用の機会を多くしている ○漁法についての紹介の画像 ○自動車工場を調べる学習において、自動車会社のHPへリンクし、動画を見て作業の様子や工程を見て学んだ |
|
| 6年 | ○学習に出てくる場所、史跡、人物等についての画像の提示 ○歴史上の人物について、動画で(当時の服装や状況なども含め)理解させる ○「大昔の人々のくらし」のソフトを活用し、昔の様子や道具を紹介する ○インターネットを使って調べる(歴史に関わる資料や画像) ○歴史上の出来事をパソコンのスライド機能を利用して提示 ○歴史学習における写真資料の提示 ○歴史…プロジェクタで歴史資料の拡大提示 |
|
| 体育 | 共通 | ○ビデオに録画しておいた動画や本をスキャンした画像をパソコンに保存。ハイパーリンクを使用して作っておき、クリックだけで見たいことが見れるようにした。(児童が自由に)あるいは、全員に提示する時にも使える 例1:幅跳びの「助走」「踏み切り」「空中姿勢」「着地」というようにポイントを分けて作る 例2:水泳の泳ぎを見せる。「世界水泳」「アニメーションで泳ぎが分かるHP」をワンクリックで見せる ○跳び箱やマット運動、スケート教室の指導と評価(ポートフォリオ的な使い方) ○跳び箱、水泳(水遊び)等…泳ぎについては、映像で見ることが児童の泳ぎの変化に大きく影響している ○跳び箱や水泳指導の参考として ○マット、跳び箱等の動作をビデオに撮る ○マット運動のポイント、回転のコツ等 ○マット運動や水泳などで、自分の姿を振り返るためにビデオで撮って見せている ○水泳の基本的泳法 ○体育館にLANを引き、マットや跳び箱などポイントがわかる(大阪市体育研究会など)資料を子どもたちがいつでも見れるようにして行う |
| 図工 | 共通 | ○「しっかりみがこう」〜自分の歯、みがく自分をよく見よう〜 導入:口の写真(全員分)…一人一人歯はちがう、みがいている写真(全員分)…磨く場所でポーズはかわる ○ポスター作成、時間割作成などのシート作り、文字デザイン、レイアウト画作成 |
| 総合 | 共通 | ○修学旅行、宿泊体験学習のプレゼンをパワーポイントを活用して行っている ○修学旅行の事前学習として、仙台松島の調べ学習の際、インターネットからとった静止画を活用 ○修学旅行のしおり作成 ○英会話学習用のビデオを作成(3年以上で視聴) ○英語…アニメの動きと発音に合わせて、ステップごとに子どもたちがまねながら、英語に慣れ親しんでいく、という内容のソフトを使い、週1時間の活動を行っている子どもたちは興味を持ち、意欲的に取り組んでいる ○カレンダー作成等…学校に関係ある画像(校舎、校庭等)を保存しておき、それらを用いて作成した ○名刺づくり…文章作成と画像、お絵かきの合成 ○絵はがき書き…画像に文章をたす ○子どもたちがデジタルカメラで撮影した静止画をテレビに映し、説明解説したり、発表に使ったりした。ビデオもほぼ同様 ○「地域の歴史を調べよう」で、古い生活用具や地域に伝わる遺跡をプレゼンテーションにして発表会を行った ○プレゼンテーションソフトを用いて、画像や動画などを提示し、発表した ○調べ学習のまとめにおいて、ワープロソフトやプレゼンテーションソフトを使い、静止画を取り入れた。たとえば、八幡平について学習したときは花や木を、学校の歴史について学習したときは、校舎や記念誌の写真をよく使った |
| 学級活動 |
共通 | ○禁煙教育の学習において、パソコンで画像や動画を提示し、視覚的にとらえさせた(保健) ○保健指導での活用 ○むし歯予防月間の指導…「6才臼歯を大切に」気づく:給食後の歯みがきの様子(ビデオ)、考える:6才臼歯のみがき方(写真)生えたばかりは小さい、みがきにくい ○歯科指導、むし歯指導での活用 |
| その他 | 共通 | ○天候が悪く、水泳や陸上の練習ができない時などに、動画やアニメーションを見せる |
|
|
| 調査結果 III (教育用コンテンツの活用が有効と思われる場面等についての提案) |
| ※教育用コンテンツの活用が有効と思われる場面等について、先生方から提案していただきました。 |
| ▲このページの先頭へ |
| 活用場面 | 学年 | 教育用コンテンツの内容等 |
| 全般的 | 共通 | ○実際に見たり、やったりできないものについて ○体育等、自分の動きを確かめるなど ○発表や他へ発信する時などの伝達の補助として ○図工などで自分の作品を蓄積していく ○観察や実験等が容易でないもの ○動作や音について理解させる必要があるもの ○実物に近い形で示したいもの ○授業の流れについての児童への説明 ○従来よりもよりわかりやすく、より広く、より効果的に発表するための方法としての内容 ○口で説明の難しい物、説明するよりパッと見て子どもが気づく要素が多いもの ○自力解決や情報収集などの場面 ○時間数の関係でも長い時間(例えばビデオ等)を見せるよりも、コンテンツを利用していった方がいいと思う |
| 国語 | 共通 | ○物語文でのイラストや挿絵の表示…物語文などの導入時に、その物語に出てくるキーアイテム的なもので実物をなかなか見せられないようなものを見せて、イメージをつかませる。例えば、「石うすの歌」の石うすで粉をひいている様子、「セロ弾きのゴーシュ」のチェロを演奏している様子 ○画像を提示し、様子を話させる活動 ○書写…教師の運筆を動画で提示し、視覚的にとらえさせる ○体を守る仕組み(4年)…抽象的な説明文を理解するための映像として活用できそうである ○漢字の書き順がわかるようなアニメーション ○原稿用紙の使い方指導 ○新聞のレイアウト指導 ○ハイパーリンクを貼らせ、動く新聞作りに挑戦させるのもおもしろい |
| 習字 (毛筆) |
共通 | ○用具の出し方、しまい方 ○筆の持ち方 ○すみのつけ方 ○基本的な書きの手本、模範→姿勢、「はらい」「はね」「とめ」など ○始筆、終筆、途中の筆使いについてのわかりやすいコンテンツ ○運筆の仕方 |
| 算数 | 共通 | ○図形の学習…四角形の分別、立体図形のとらえ ○図形領域における概念形成において ○図形の指導(つまづいている子への支援) ○図形やグラフの問題提示、まとめでの活用 ○図形領域のコンテンツ…平行四辺形、三角形の面積の求め方 ○角の大きさについて ○三角形の種類…二等辺三角形、正三角形、直角三角形 ○平行四辺形の面積の求め方で、長方形に作りかえてアニメーション機能を使って説明されていた。わかる授業の支援としては、アニメーション機能は工夫次第で有効なものとなると思う。このようなストックをたくさんふやしていければと思う ○体積や面積の動画(考え方) ○操作活動等の理解…ブロックや半具体物等の操作を動画として、児童がすぐに見られるように ○用具の扱い方について、動画としてライブラリーのようなものにする ○筆算の仕組みを図(タイル図等)のアニメーションで確認する ○ひっ算の仕方(視覚的に計算の流れが見えるもの) ○コンパス、ものさしなどの使い方を一斉に指導するとき ○コンパスの使い方、平行な線の引き方等、スキルに関わる動画 ○コンパスや三角定規の使い方など、手元をアップで見せたいとき ○作図指導…コンパスや定規の使い方の導入時に、実際に動画を見ながら操作するようにするといいのではないだろうか ○線の引き方…ものさしを用いて、ある長さの線をひく ○コンパスで円を描いたり、模様を書いたりする場合の動画 ○公式の復習…学期末などにすでに習ったことの復習や確認などに、教育用コンテンツまたはプレゼンテーション等が有効かもしれない ○フラッシュカードの代わりに(かけ算九九等) ○難しい文章題の文意が画像によって提示されることで、下位層の児童の理解を助けるコンテンツ ○立体の透視図を画像で示し、視点を変え、いろいろな角度からその立体を見ることで、教科書の透視図をどうしても三次元でとらえにくく、二次元で見てしまう児童の理解を助けるコンテンツ ○量と測定領域のコンテンツ…水のかさ演示用、長さ、縮尺、体積等 |
| 生活 | 共通 | ○用具の正しい使い方など ○昔の道具の使い方 ○学習したことを再確認する写真や地図 |
| 理科 | 共通 | ○実物を提示できない場合のコンテンツ ○動画をあらゆる単元で ○体内のこと、地球内部のことなど実際には見ることができないものを見ること ○こん虫、草花(発芽や生長)、地形、月や星の動き ○栽培や飼育の学習上、児童に見せたい場面がタイムリーに時間割の授業時間と合う訳ではないと思うので、短時間に編集しておいて活用していきたい ○観察…動植物のコンテンツ ○植物の成長、生き物の体のつくり等、生物全体で活用できると思う。やはり、動画が有効ではないか ○生物の成長過程を映像でとらえる場合 ○観察実験の記録の保存 ○植物の芽が出る成長過程…芽が出るまでの様子を動画で見せる。または、静止画で主な場面を紹介する ○植物の開花、成長、四季の変化への適応等、時間や期間のある事象を短くまとめたコンテンツ ○植物の成長の様子、天気図の変化の様子、太陽・月・星の動きなど、あらゆる領域で使用できると思います ○植物の成長や宇宙(星や月)など、映像でなければ見ることができないもの ○植物、動物、自然現象、実験法等の画像等での提示 ○植物の成長過程、季節の花、実験(道具がない場合)、星座、月など、口で説明しなくても自ら気づけるようにする ○植物の成長について実験観察するとき、実際に実験観察したあとに活用する(実験がうまくいかない場合もある) ○植物の発芽と成長の倍速動画など ○植物・生物の育ち方…アサガオ、チョウ、メダカの成長過程 ○長期の観察…メダカ、へちま、アサガオ等 ○天気の変化やメダカの産卵等、あまりよく観察しにくい物を見るのに有効 ○こん虫の成長過程…卵から成虫になるまでの様子を動画で紹介する ○昆虫の飼育 ○長期間にわたる観察(動画) ○実際に育てられない、育たない場合、実験が思うようにいかなかった場合などに活用できると思われる。でも、やっぱり体験するのが一番 ○空気など目に見えないものの実験 ○地学のさまざまな具体例やモデル ○実際に体験できないもの等、教育用コンテンツを利用していけば良い。具体的にはまだイメージがわきませんが ○人のたんじょう、植物の発芽など…栽培や実験などが失敗してしまった場合に利用したい ○太陽系、地球の誕生 ○実際に見られないもの…大地の変化、天気図 ○時間のかかる実験観察。危険が予想される実験。地理的に無理な観察等 ○天体、気象、地層など簡単に観察できない内容、実験実技に関する内容 ○実際に見ることができない動物の体の仕組みなど ○実物を観察したり、実験したりするのが困難なもの ○日常生活では目にすることができない映像 ○従来、ビデオ等を使い示していた植物の成長、生き物の動き、体のつくり等を効率的に提示できる ○学習の発展として…授業時間の中では見ることができなかったものを動画で見ることにより、これまでにはできなかった学習内容の充実が図れると思う ○各種実験や観察…各種の観察、実験では、観察・実験器具の操作方法の説明に結構な時間を費やすことが多い。また、誤った操作方法でうまく実験できない児童も見られることから短時間で、具体的に理解できる映像があるとよい(各学年ごとに) ○実験方法を確認する際に活用すると、手順等もはっきりするのでは ○実験の仕方や道具の扱い方など、授業の始めの10分等、一部分で扱える内容 ○実験の操作方法、手順、注意点を動画で確認する ○実験方法の提示 ○実験器具の使い方の説明 ○危険を伴う実験…水溶液 ○観察の記録、器具の使い方 ○授業ではできないような発展的な実験や危険な実験の映像 ○実験…一瞬で終わってしまう、動きをしっかり動画で ○実験の内容、手順、結果、発展学習など ○実験器具の名称、使い方 |
| 3年 | ○こん虫の育ち方…体の仕組みの説明(卵→幼虫→さなぎ→成虫) ○実際に見れない内容や場面…理科では3年生の「植物の成長」「モンシロチョウ」と生きた物が必要となり、いずれも種の発芽、卵からの育つ過程が大切である。できれば動画を使用したい。また、まとめで振り返るところでの活用も考えたい ○3年の生物の成長の様子をデジカメで撮り、観察カードのように積み重ねていき、パワーポイント等でまとめる |
|
| 4年 | ○ヘチマの成長…ヘチマが芽を出して、つるが伸びるところ ○「月と星」など、実物を見せながら学習したいが不可能(教師がついて解説するなど)な場合…「理科ネットワーク」などインターネット上のもの、市販のソフト ○月や太陽の動き方について長時間にわたって観察を要するものについて、短時間に編集し提示する ○「月・星」…星空を撮影したものを日中でも学習できるようにする ○月の動き…月の動き(アニメーションと動画(実写)の組み合わせ等) ○夏・冬の星…星座の動き(くりかえして見られるように) ○星の学習…実際に夜空を一緒に観察し、まとめることができないので、どうしてもビデオ教材になってしまうが、やはり定着しない。何かよいものはないか、いつも指導に悩むので教えていただきたい ○星座(季節に合わないものの提示) |
|
| 5年 | ○川や大地のつくりの学習の中で…地形のでき方をシミュレーションできたらいいと思う。その様子を短時間のうちにまとめて提示できそうだ ○「1日の天気と気温の変化」気象衛星の画像や天気図の画像によって、天気の変化のきまりをつかんだり、天気の予想をしたりする ○天気図、雲の画像の活用 ○気象情報の画像 ○メダカの飼い方 ○メダカの卵の変化など、細かな変化を観察(心臓の動きや血液の流れなど) ○メダカの卵の観察。人の誕生(受精後の成長過程など) ○顕微鏡の使い方 |
|
| 6年 | ○地層の学習など、実際の見学が難しい内容 ○地層など見られないもの ○地層の学習…静止画でいろいろな地層を紹介する ○地層→長い歴史の中に位置付ける(実際に現地で観察することが難しい) ○地層の学習(川の流れとか)…地域的な理由で、学校の近くに路頭がない場合、地層に関するコンテンツがあればいいと感じる ○動物と人のからだ…消化、呼吸等の最新の生体映像や特殊撮影映像 ○動物のからだの作り…「人体の内部のつくり」魚の解剖といった手段もあるが、コンテンツによって人体の様子を立体的にとらえることができる ○大地のつくり…火山噴火の映像 ○大地のつくり…「地層の重なり方」器具を用いた実験もあるが、うまく層ができにくい。また、隆起や沈降といった動きも見ることができる ○鍾乳洞 の画像 |
|
| 社会 | 共通 | ○写真資料もしくはグラフ等の変化のあるものの提示 ○実物を提示できない場合、それにかわるコンテンツ ○交通の広がり…「県の白地図」コンピュータ上に白地図を呼び出し、鉄道、高速道路、航空などの交通手段を彩色させる。地形についても様々な角度から見た画像を見ることで、より実感できる ○産業(工場の様子)、農業(畑の様子、収穫等)、歴史(絵の中から当時の様子をさぐる) ○施設等の紹介、郷土の歴史的遺産等の紹介 ○まとめの場面や課題を見つける場面で利用する ○他の地域や外国の様子など、実際に行ったことのない映像を見ることは、大変意欲付けになると思った ○昔の道具の使い方の動画 ○地図や図形など、その場に行けない時に画像を見せる ○映像により具体的にイメージしやすい(戦争、くらし等) |
| 3年 | ○3年の地域の人とのインタビューなど、字幕を付けたり、説明のグラフを入れるなど、分かりやすい資料として作る ○商店街の様子、図書館など、地域によって近くになく見学に行けない公共施設の動画 |
|
| 4年 | ○地域によって近くになく見学に行けない公共施設の動画 | |
| 5年 | ○工業の学習の中で…自動車の製造ラインを紹介したものがあれば、子どもたちの興味関心を高められそうである(実際に見学に行くことが難しいので) ○水産業の様子(海がないところは、動画がほしい) |
|
| 6年 | ○歴史の近代史で映像資料(主に動画)として活用すれば、より子どもたちの理解が深まる ○人物写真、絵巻、昔のくらしの様子、建物、服装、道具等を提示し、視覚的効果をねらう ○歴史的資料(画像等)の提示 ○風俗、環境などについての資料の提示(歴史) ○貴族のくらし…平安時代の貴族の衣装や寝殿作りの様子等、資料を静止画で紹介する |
|
| 音楽 | 共通 | ○形態の紹介の画像 ○歌唱…口の開きと発声の違い、表情、呼吸法の動画 ○口の開け方、楽器(リコーダーやピアニカ)の指の使い方を動画で確認する ○楽器の紹介の画像 ○楽器の演奏(手の動き等)の範例 ○器楽…リコーダーの奏法、音楽記号と実際の演奏例、楽器の音色、演奏の様子 ○楽器の種類、音色、演奏の様子…音楽科では、曲や楽器のイメージをしっかりと持たせることにより、その良さをとらえさせ興味付けを図ることが大切である。その意味で、楽器の種類や音色、演奏の様子等のコンテンツは、大きな意味があると考える。県音研のウィンターセミナー等でも紹介したい ○リコーダーや木きん、ドラム等の基本やスキルの動画 |
| 図工 | 共通 | ○製作過程の提示 ○デジタルカメラの利用(画像での構図指導) ○木版画の制作過程 ○よい作品などの画像紹介 ○世界の名画やふだん見ることのできない作品の鑑賞 ○初めての絵の具学習において、パレットの使い方や筆洗いの仕方等を視覚的にとらえさせる ○絵の具セットの使い方 ○用具の正しい使い方など ○彫刻刀の使い方 ○ポスター指導(下絵をトリミングする場面)…下絵を一度コンピュータに取り込み、コンピュータ操作で何カ所かをトリミングし、それを画面で確認しながら、下絵のどこの部分を大きく描けばもっとも良いかを考えながら、本絵描きに至る指導 |
| 体育 | 共通 | ○動画によるよい動きや自分の動きの確認(比較と修正) ○提示資料として実物を用意できないものや小さくて分かりづらいもの等をプロジェクタ等を通し、視覚的にとらえさせたい場合に有効 ○音楽と同じように、よいものにふれる必要があると思う。陸上運動や水泳で、自分のフォームと比較するもよし、お手本にするもよし ○運動領域でのポイント指導に活用できる ○運動を場面ごとに分けて提示 ○動きのポイントをつかむために映像を見せる ○場の工夫ももちろんだが、課題に対して取り組む過程で、いつでも子どもたちがコンテンツを見られる環境を作る ○特にも難しい技の手本 ○その場で作成して、みんなで見合えるようにする ○自分の動きを確認できる(陸上、器械運動等) ○技のポイントの例示 ○模範演技…水泳、陸上、器械運動 ○運動技能のポイント、動きを具体的に示すことができる ○新しい技への導入として使える ○基本の運動…各種の運動のポイントを紹介した教育用コンテンツ ○マット運動等で実際に映像を見せると技を理解しやすいのでは ○マット運動…手のつき方や頭の位置などを動画を使って指導 ○マット運動でお手本と自分の動きを比較し、自分のなおすべき点を見つけ練習に生かす。例えば、開脚前転で、お手本の動きと自分の動きを両方同時に比較しながら見られるようなものが(児童が自分で簡単に操作できるとなおよい)体育館にテレビを持ち込むより日常的に使えると思う フォームのイメージをつかませる上では、静止画が大いに活用できると思う ○跳び箱、マット運動、陸上、水泳等の正しいフォーム等の提示 ○跳び箱、鉄棒(逆上がり)、水泳…とべる子のポイント、とべない子はどうして。ワンポイントレッスン等 ○マットや跳び箱で、子どもたちのフォーム等を録画し、スロー再生・停止をしながら確認 ○マット運動、跳び箱運動、鉄棒などの技のポイントを連続映像で指導できるもの ○マット運動での動きをスローで見せることによりポイントをつかませる ○跳び箱などで範例と子どもの動きを重ね合わせて比較するなど、模範を示せないような場合の動きのイメージ化として ○跳び箱やマット運動の正しい技と児童の実態を見比べさせて、ポイントを指導する ○跳び箱、マット運動…手のつき方や体のどこをどうするか等 ○跳び箱やマット、鉄棒などの技能を指導する場面で有効。特に、空中(?)での姿勢や 実技を行う前のお手本として。また、自分の演技をビデオに撮り分析する ○鉄棒、跳び箱、水泳など実際では子どもたちに説明しづらいものの動画 ○器械運動や水泳指導での活用 ○鉄棒(逆上がり等)の動画 ○鉄棒、マット、跳び箱、水泳などの実技のこつがわかる内容 ○鉄棒、マット運動、跳び箱…側面、前面からの動作、ポイントとなる部分の解説 ○器械運動、陸上等でのフォームの紹介、練習方法の提示 ○器械運動の技の習得に有効な運動や練習の場の提示 ○実技…器械体操(マット、鉄棒、跳び箱)、陸上、水泳 ○器械体操…動きの速いものなど効果的と思われる(跳び箱、マットなど) ○跳び箱運動や水泳学習…模範となる動きを見ることにより、自分の運動能力を高めることができる。また、自分の運動をビデオで撮り、比べることにより、次の目標を持つことができる ○水泳、跳び箱、マットなど画像を用いて指導・分析・練習することは大変効果的である ○水泳の動画 ○今日、平泳ぎの手のかき、足の動き等の動画を用いた指導場面の提示があった。上下、横方向、様々な角度から動きを見せられることは、器械運動等の指導にも役立つであろう。他にもマット運動、鉄棒運動などで有効と考える ○水泳や跳び箱の手本 ○水泳、陸上をはじめ、多くの技能面について活用できる(子どもたちの様子を録画したものから処理できる) ○水泳の導入…水中からの撮影による手の動き、足の動きなどを見ての児童による課題設定 ○水泳、マット運動の手本のコンテンツと子どもたちの動き(自分)を撮影したコンテンツを作り、比べてみると効果的だと思う ○水泳の導入…泳ぎ方の確認等 ○水泳、器械運動…正しい動作や補助等の仕方、そのポイント指導 ○水泳や跳び箱、マット運動など説明しながら試技をするのは難しいので、動画を見せて、いろいろな角度からのポイントを指導できると思いました ○水泳指導…手のつかい方、足のつかい方などを動画を使って指導 ○水泳学習…各種の泳法のポイント「クロール」「平泳ぎ」「背泳ぎ」「バタフライ」等 ○陸上運動…走法、リレー、高跳び、幅跳び、ボール投げ、トレーニング法 ○ボール運動…バレー、サッカー、ハンドベースボール、バスケなどの演技、説明 ○けがの手当(すりきず、きりきずなど)の動画 |
| 家庭科 | 共通 | ○製作過程の動画での提示 ○なみぬい(針の持ち方、布の持ち方等)の画像 ○玉どめ、玉結び、なみぬい、返しぬい等の手ぬいの仕方の動画 ○ミシンぬい等の物作りの動画 ○ミシンを使うときに、上糸のかけ方や下糸の出し方などの動画を活用する ○ぬい方、包丁の使い方等の動画 ○調理の仕方、手縫い(なみぬい、本返し、半返しぬい) ○調理技能の画像 ○用具の使い方の動画 |
| 総合 | 共通 | ○子どもたちが疑問をもつような場面、画像を用意する→導入での意欲付けに使う ○まとめの場面…自作資料を活用した映像作り。例えば、画面を教師が作成し、音声を子どもたちがアフレコで入れるなど ○英語学習(国際理解教育)…いろいろな場面を設定したものがあれば、自分で操作しながら発音したり、お互いにそれをもとにして、交流授業ができるのではないかと考える ○英語学習…テレビ電話のような形で ○国際交流…文化の違いを比較するようなもの(言葉、習慣、衣服等) ○太陽系、地球の誕生の画像 ○生命の進化の画像 ○海の生き物を紹介する場面…まとめとして、子どもたちに活用させたい。コンテンツを利用したまとめであれば、子どもたちのコンピュータ活用の技術もつくのではと考える ○水質調査、我が国の福祉の現状等 |
| 道徳 | 共通 | ○資料、補助資料の提示 ○映像資料 ○岩手の先人について、パワーポイントにまとめたもの(授業で活用できるもの) |
| 学級活動 | 共通 | ○プレゼン(議題提示)として |
| 情報交換 | 共通 | ○今の学校に専門的な知識を持っている先生がいない場合、子どもの学習の様子や学習材をコンテンツとして作り、メール等で専門の先生にご覧いただき、修正や指導を得る |
| 特殊教育 | 共通 | ○今までは実物を用い、教師が示したり、ビデオを活用することが多かったと思う。パソコンの簡単な操作が身に付けば、そのような子どもが自分でコンテンツを見ながら、学習を自らのペースで進めることができるのではないか |
| 集会 | 共通 | ○何かやり方や手段を教える際に活用する。例えば、多人数のいる中で教師一人が何かをやってみせるとなかなか見えにくかったり、わかりにくい。そこで、全体に見えるようにコンテンツを大型プロジェクタに投影して見せる |
| 作品交流 | 共通 | ○校内の中のホームページにアップして、いつでも見られるように、デジカメやスキャナ等で撮影しておく |
| 実技指導 | 共通 | ○図工…絵の具、はさみ、のり等の扱い方 ○音楽…けん盤の扱い方、ひき方 ○体育…理想的なフォーム、まちがったやり方 ○家庭科…調理の仕方、ぬい方 ○理科…実験方法 ※今までは、一斉指導では見にくくて、個人やグループで指導していたもの ○やり方や注意すべき点、コツなどをとりまぜた映像を自由に見ることができるようにする |
| 複式授業での自力解決 | 共通 | ○算数の大きな数(例えば、100以上、1000以上)の導入の時の数を数える時に使えそうなもの |
| 掃除用具の使い方 | 共通 | ○ほうきの使い方、ぞうきんのしぼり方、掃除機の使い方、ガラス拭きの仕方、給食の盛りつけ方 |
| 遊具の乗り方 | 共通 | ○竹馬の上手な乗り方、わざの紹介 ○一輪車に乗れるようになるまでの練習方法、わざの紹介、なわとびのわざの紹介 |
| コンピュータ | 共通 | ○デジカメの使い方、スキャナの使い方、印刷の仕方 ○キーボードの操作やファイルの保存の仕方 |
| 環境教育 | 共通 | ○ごみの分別の事前指導…主なゴミを「資源ゴミ」「燃えるゴミ」「不燃ゴミ」等の場所に移動させる |
| ことばの指導 | 共通 | ○構音指導全般 |
| その他 (意見等) |
共通 | ○教育用コンテンツは役立つと思うが、現在、小学校の学習に役立つコンテンツは非常に少ないと思う。豊富にそろっていないと学習に役立てることはできない(教育の共通財産として、作ったものを持ち寄ったり、登録すればよい) ○簡単に見せられない映像を、たくさんサーバーに入れておけば、校内LANを活用してすぐに見せられる |
|
|
| ▲このページの先頭へ |